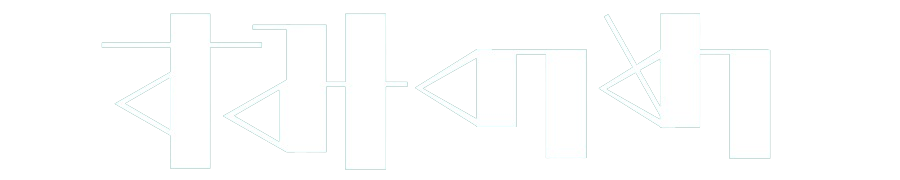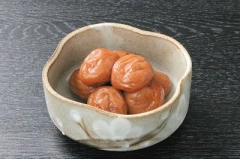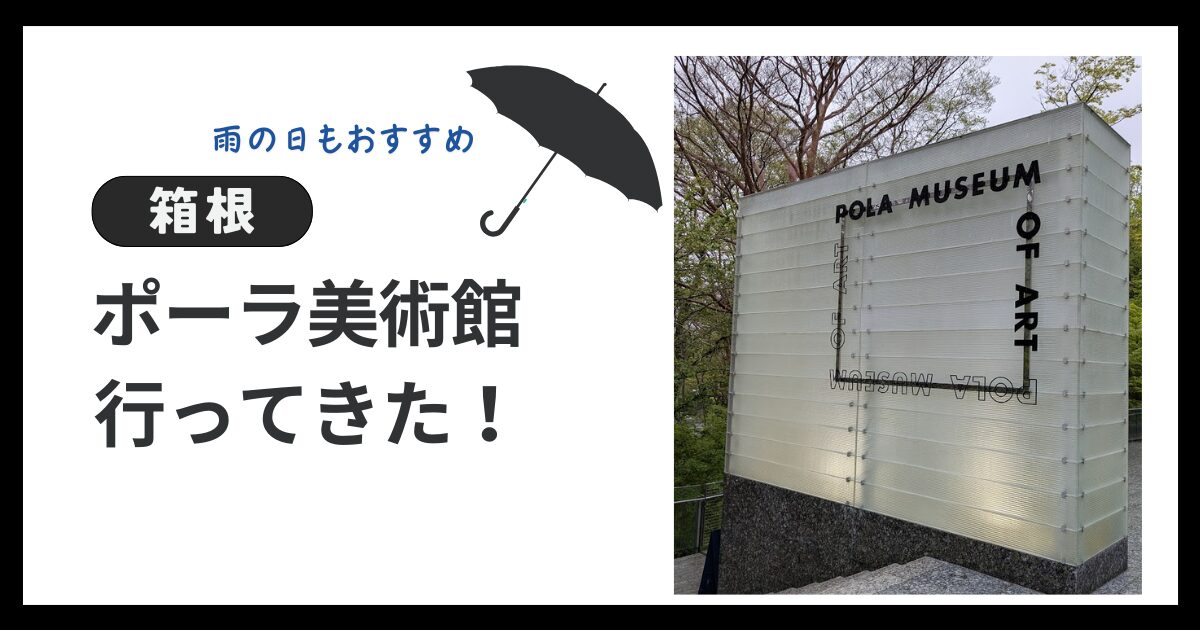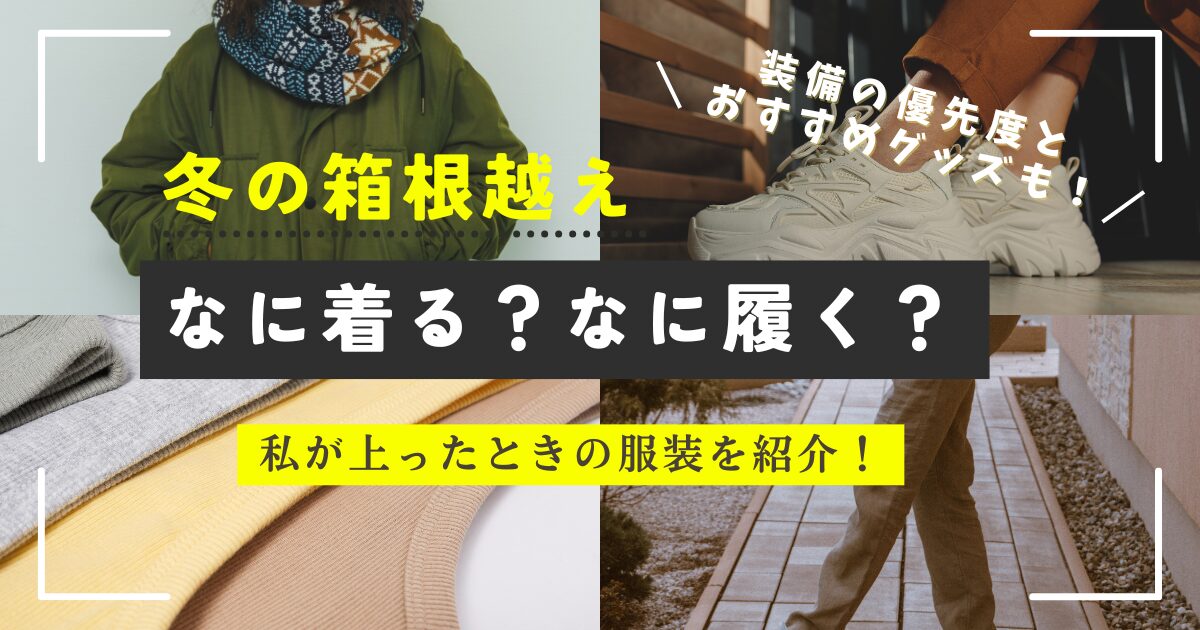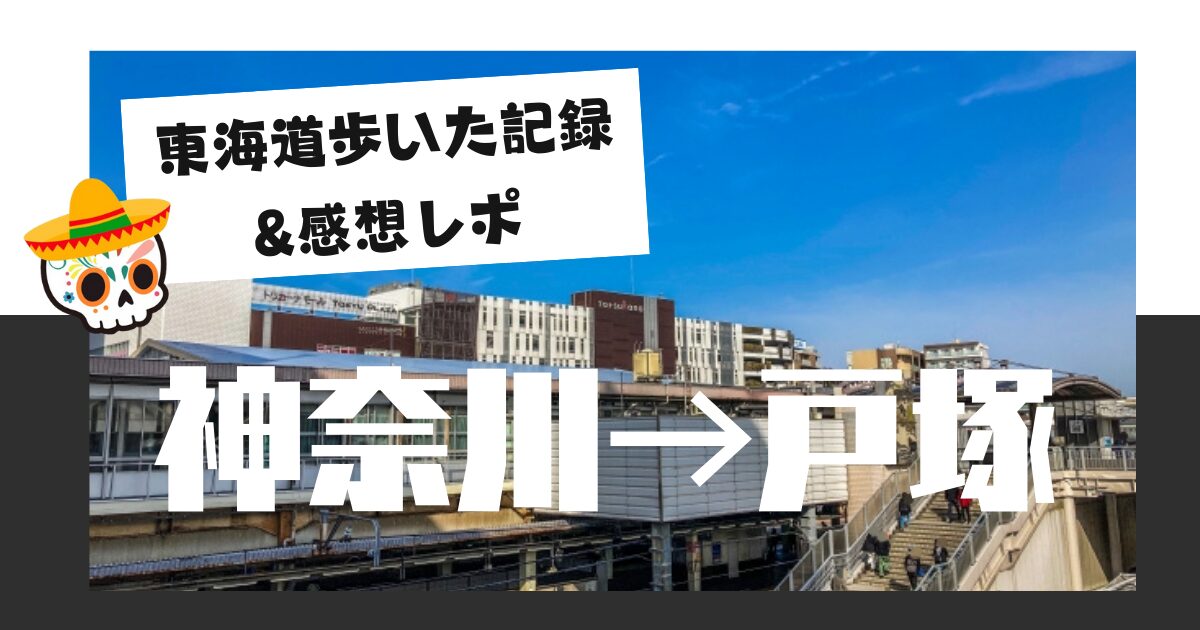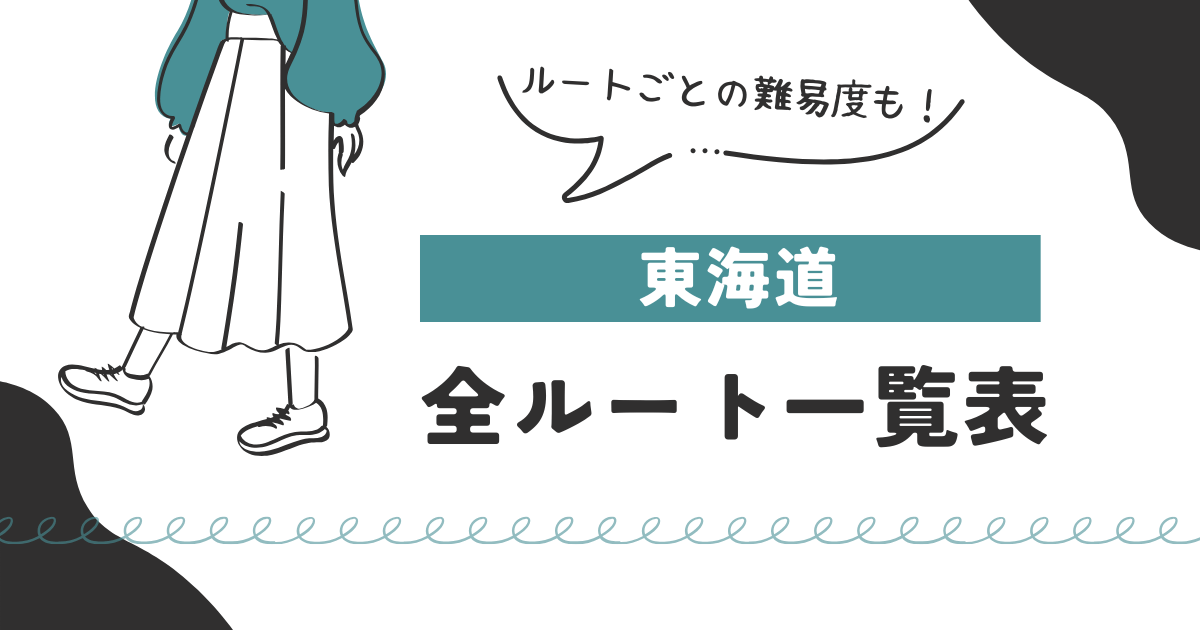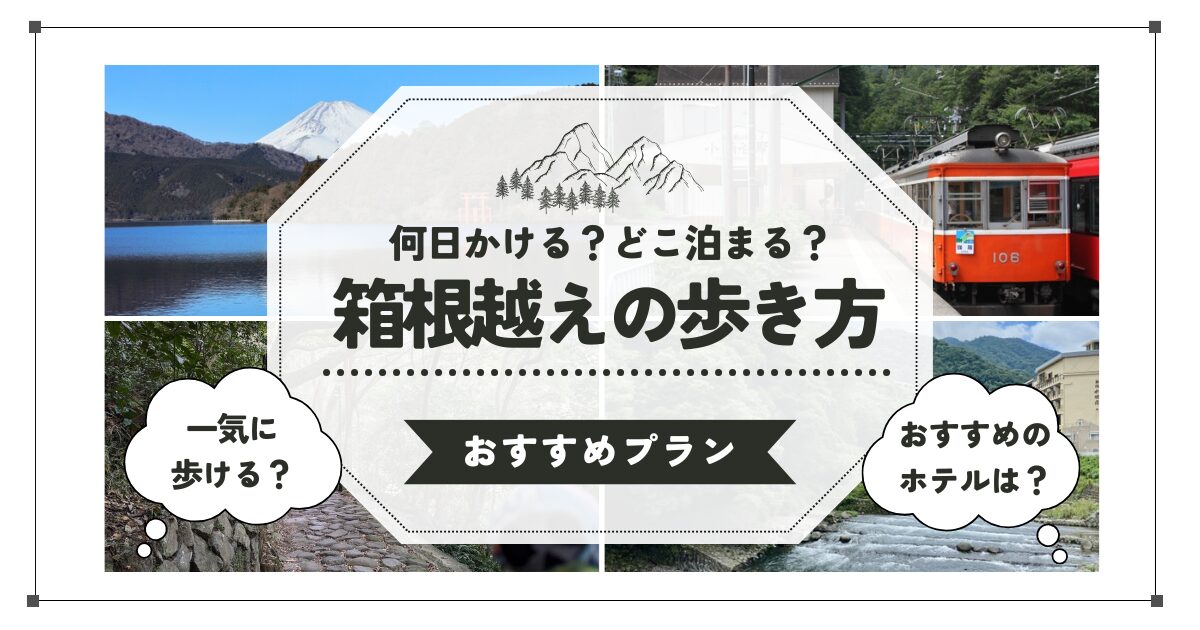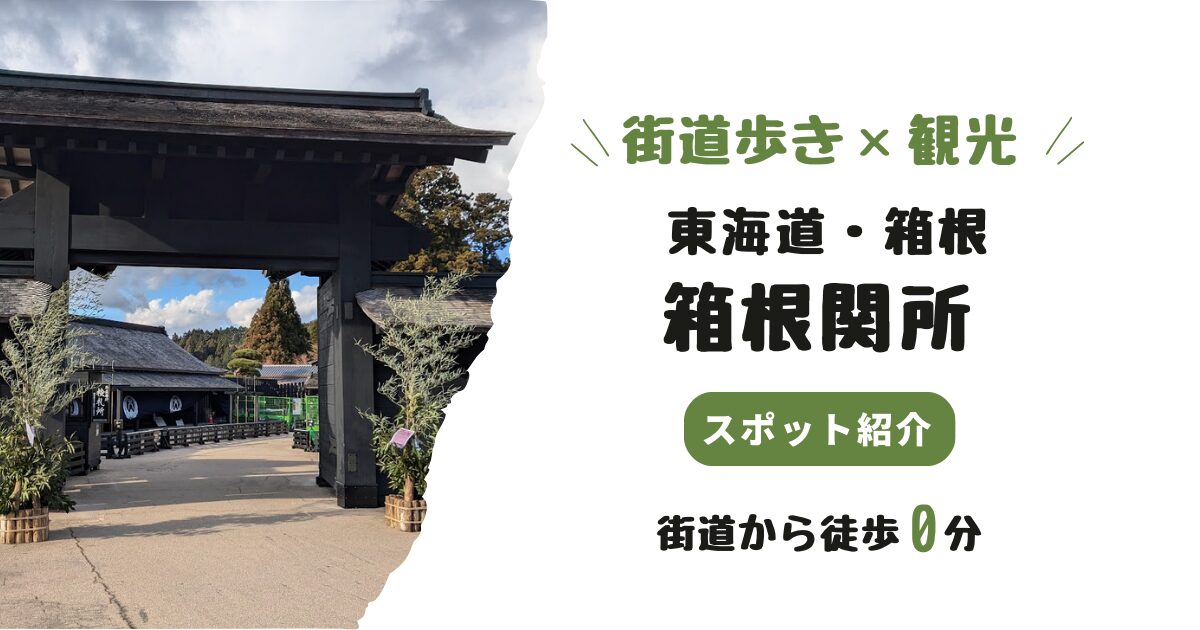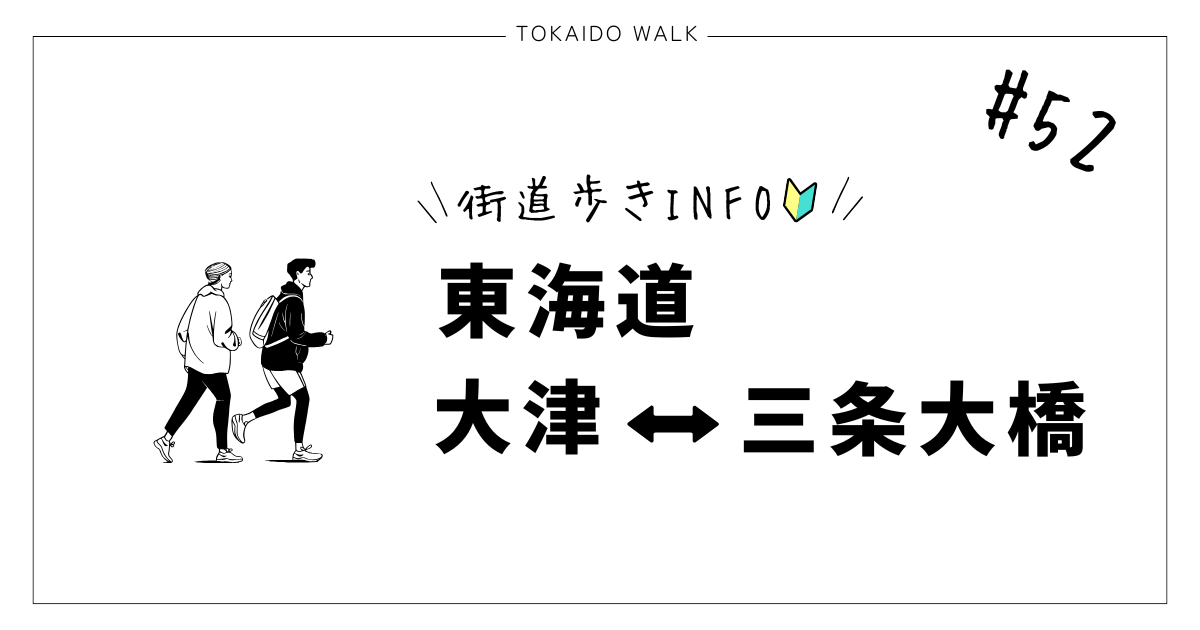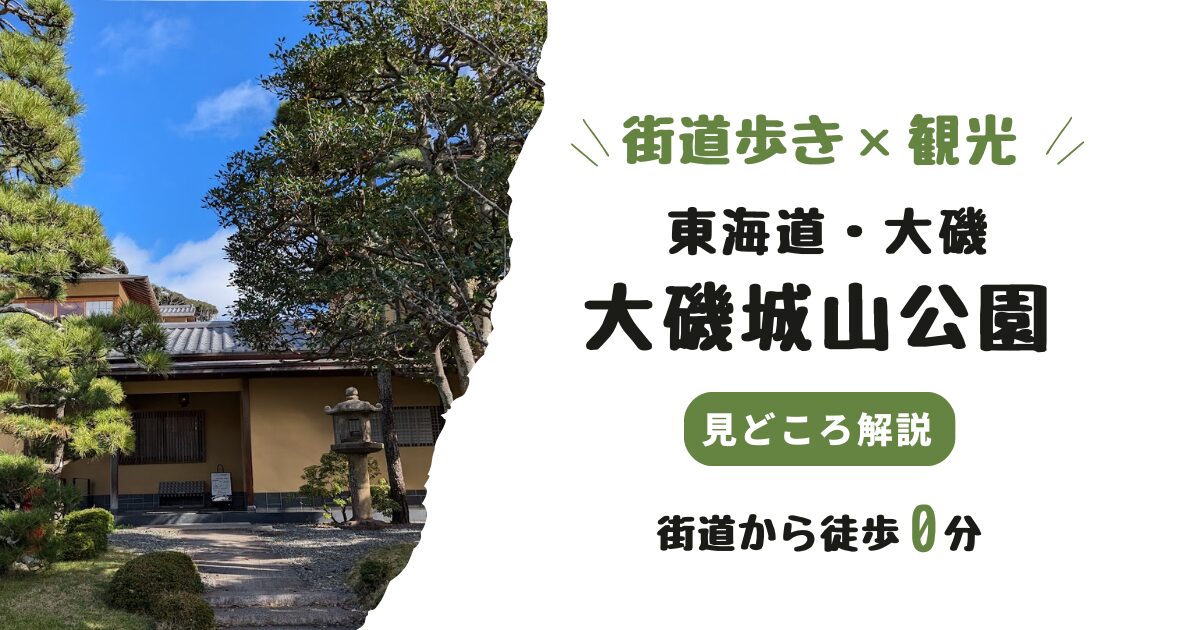小田原は古くから、たくさんの人とモノが行き交い、東海道の宿場町として賑わっている町でした。
「小田原にきたら、これを食べるべし!」という名物グルメも、かなり昔からあったようです。
江戸時代から現代まで、特に有名な小田原名物は、かまぼこ・干物・ういろう・梅。
この記事では、この4つの小田原名物のおすすめ店を、厳選して紹介しています。
なるべく老舗の名店をチョイスしているので、失敗したくない初心者に特におすすめのお店ぞろいです!
小田原名物① かまぼこ

江戸時代から現代にいたるまで、小田原名物と言えばまず出てくるのが、かまぼこ。
相模湾に面した小田原は、古くから漁業が盛んな地域でした。
しかし当時の保存技術では、新鮮な魚を長持ちさせることができません。
そのため保存食として、魚を腐りにくいよう加工したかまぼこ作りも広まったのです。
おすすめのかまぼこ店
市内には、かまぼこ専門店が立ち並ぶ「かまぼこ通り」もあり、お店はかなり多いです。
その中でも、老舗かつ知名度の高い、かまぼこの名店をピックアップしました。
| 店名 | 創業 | 本店エリア | 駅前にお店 | オンラインショップ |
|---|---|---|---|---|
| 鈴廣 | 1865(江戸末期) | 風祭駅 | ○ | あり |
| 籠清 | 1814(江戸後期) | かまぼこ通り | ○ | あり |
| 鱗吉 | 1781(江戸中期) | かまぼこ通り | ✖ | あり |
| 山上蒲鉾店 | 1878(明治初期) | かまぼこ通り | ✖ | あり |
本店はどこも少し駅から離れるけど、小田原駅の近くに支店を出しているところもあるよ
荷物にしたくない場合は、ネットで買っちゃうのもあり!笑
鈴廣(すずひろ)
籠清・丸う田代と並ぶ、小田原かまぼこ御三家の一つ。
無添加にこだわった、職人によるかまぼこ作りが特徴です。
小田原駅から車で10分、本店がある「鈴廣かまぼこの里」は、観光スポットとしても有名。
レストランやカフェ、蒲鉾づくりの体験、博物館などがあり、かまぼこを「見る・食べる・学ぶ」が総合的に体験できます。


小田原のかまぼこ店と言えば、「鈴廣」が一番有名なイメージ
僕も小田原のお土産に、鈴廣の焼きかまぼこをもらったことがあるよ~
籠清(かごせい)
鈴廣・丸う田代と並ぶ、小田原かまぼこ御三家の一つ。
創業時から続く製法を守り、水・魚・石臼・浄水にこだわった、かまぼこ作りが特徴。
普段用はもちろん、最高級蒲鉾「鳳凰」など、贈答用の高級品も充実しています。
本店は、昔ながらの格式高い雰囲気があって良い感じ
かまぼこ通りの中でも、風格のあるお店だよ
鱗吉(うろこき)
創業は江戸中期、小田原かまぼこ発祥のお店と言われている老舗かまぼこ店。
昔ながらの石臼作りにこだわり、歯ごたえと弾力感を大切にしています。
本店では、併設された飲食スペースで、足湯につかりながらかまぼこや日本酒を楽しめるのが特徴。
本店は、地酒・地ビールも充実。酒飲みにはたまらない
山上蒲鉾店
全国かまぼこ品評会の農林水産大臣賞を通算5回受賞した、老舗かまぼこ店。
化学調味料無添加、身体に優しい素朴な味付けが特徴です。
伝統的なかまぼこの製造技法にこだわり、魚の仕入れから製造まで全てを市内の自社で行っています。
このお店の職人の一人は、小田原では初の、厚生労働省「ものづくりマイスター」に選定されたよ
少人数の職人集団が作る、確かな味のかまぼこ店!
小田原名物② 干物


かまぼこと同じく、小田原の干物も、豊富な魚を活かした名産品として有名です。
特に有名なのは、アジの干物。
江戸初期に記された食物本「本朝食鑑」に、小田原のアジの干物を絶賛した記述が残っています。
おすすめの干物店
山安
1863年の創業以来、小田原ひものを牽引してきた全国有数の干物専門製造業者。
厳選した天然天日塩を使い、魚本来の味を引き出すのがこだわりです。
小田原駅前店をはじめとして、市内に何店舗もお店を出しているので、アクセスが良いのがおすすめ。
ターンパイク店の2階には、山安食堂(山安の干物が食べられるお店)もあるよ
早瀬のひもの
創業以来、防腐剤を使わない、無添加にこだわった甘塩での干物づくりにこだわっている専門店。
店舗は少し駅から離れますが、たくさんの種類の干物を扱っています。
近くには、干物を使った弁当やバーガーが楽しめるお店、himono stand hayaseもあるよ
ひもの屋 半兵衛
すべての干物は手開き加工、職人が塩の漬け時間を調整し、手作業で製造している専門店。
お店は小田原駅から少し離れた、早川港の魚市場にあります。
工場直営なので、お得にたくさん干物を買えますよ。
小田原名物③ ういろう


江戸時代には、小田原名物として一番有名だったとも言われるのが、ういろう。
甘い味付けのお菓子である「ういろう」以外に、薬効のある薬としての「透頂香(ういろう)」も名物でした。
江戸時代に大ヒットした十返舎一九の小説「東海道中膝栗毛」でも、主人公が小田原宿で、
「ういろうを 餅かとうまくだまされて こは薬じやと苦い顔する」
十返舎一九「東海道中膝栗毛」
というシーンがあります。
おすすめのういろう店
| 店名 | 創業 | 小田原駅から | オンラインショップ |
|---|---|---|---|
| ういろう | 1368(南北朝時代) | 徒歩15分 | なし |




小田原のういろうと言えば、このお店一択。
創業から650年、小田原最古の店舗「ういろう」です。
このお店の初代・外郎(ういろう)家が、1300年代に中国から京都に持ち込んだ家伝薬「透頂香(とうちんこう)」が、ういろうの起源です。
元々は丸薬として非常に評判が高く、後にお菓子として創作した「ういろう」も名物となりました。
戦国時代に京都から小田原に拠点を移し、以後500年以上、小田原名物・ういろうの販売をしています。
薬のういろうは、店頭販売のみだよ
お菓子もオンラインショップはなし。電話すれば発送対応はしてくれるみたい
小田原名物④ 梅


小田原は、戦国時代から梅の栽培でも有名な地域です。
小田原を支配した戦国大名、北条家初代の北条早雲は、梅干しの薬効に注目して、梅の木を植えて梅干し作りを奨励したとか。
江戸時代は、東海道を歩く旅人の携帯用の食べ物としても、需要が高まりました。
こちらも同じく、東海道中膝栗毛に小田原名物として登場します。
「梅漬の 名物とてや とめおんな くちをすくして旅人をよぶ」
(訳:小田原の名物が梅漬であるためか、とめ女が、くちをすっぱくして旅人を呼ぶ)
十返舎一九「東海道中膝栗毛」
小田原ブランド梅「十郎梅」
小田原の北東部には、曽我梅林という梅の産地があり、約35,000本が栽培されています。
小田原の梅干しと言えば、この曽我梅林の梅干しのこと。
中でも多く栽培されている「十郎梅」は、小田原オリジナルのブランド梅。
果肉が厚く肉質が柔らかい、梅干し用の最秀品です。
品種ごとに違う味わい。曽我の梅干しを食べ比べるのも良いね
曽我梅林の周りには、梅の直売所も何軒かあるよ~
おすすめの梅干し店
| 店名 | 創業 | オンラインショップ |
|---|---|---|
| ちん里う | 1871(明治初期) | あり |


小田原駅前に本店を構える、梅干し専門店。
十郎梅をはじめとする、曽我の梅干しを多数取り揃えています。
梅干しパウンドケーキや梅ブラウニーなど、梅を使ったお菓子類も人気。
まとめ
この記事では、「江戸時代から続く」という基準で名物をピックアップしました。
小田原おでんやスイーツなど、他にも名物は色々あるので、そちらも要チェックですね。